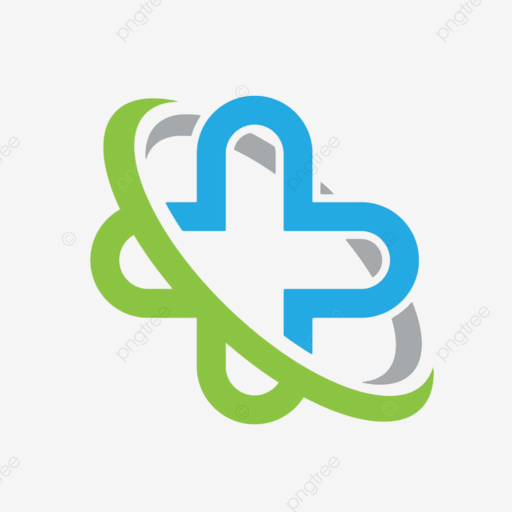強迫性障害とは

強迫性障害とは、自分の意志とは裏腹に不安や不快な思考が繰り返し頭に浮かび、それに対応しようと特定の行動や儀式を繰り返してしまう心の病気です。
たとえば、家のドアをきちんと閉めたはずなのに不安になって何度も戻り確認する、手に汚れが付いた感覚が拭えず、頻繁に手洗いをしてしまうといったケースがよく見られます。
こうした症状は、本人自身も不合理だと理解しつつも、止められないことが特徴です。
強迫性障害は思春期や若い成人層に発症しやすいとされていますが、早期に適切な治療やサポートを得ることで、日常生活への負担を軽減しやすくなります。
そのため、心当たりのある方は、ためらわず専門医に相談してみることをおすすめします。
当院でも一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っていますので、安心してお声かけください。
強迫性障害の主な症状

強迫性障害は、本人の意思とは無関係に頭の中に生じる思考やイメージ(強迫観念)と、それに対応して繰り返される特定の行動(強迫行為)の、2つの特徴があります。
これらは単なる悩みや癖とは異なり、日常生活や社会生活に重大な影響を及ぼすことも少なくありません。それぞれの特徴を確認していきます。
強迫観念とは、突然浮かぶ否定的な考えや不快なイメージ、あるいは根拠のない不安などが繰り返し頭を占領し、自分の意志ではその思考の流れを止めることができない状態のことです。
「もしドアの鍵をちゃんと閉め忘れていたら…」という恐怖や、「自分の手には目に見えない汚れが付いているかもしれない」という疑念が執拗に現れることが例として挙げられます。
このような思考は、多くの場合無意味だと理解していても強い苦痛をもたらし、結果として生活全体の満足度が著しく損なわれる原因になります。
強迫行為とは、強迫観念によって生じた苦悩や不安感を打ち消そうとして本人が繰り返し行う行動です。
本人にとっては一時的に安心感を得る手段になっていますが、多くの場合「こんなことをしても無駄だ」と理性ではわかっているのが特徴です。
例えば、外出前に何度も鍵を確かめたり、特定の順序で物事をやり直したり、過度に手を洗い続けたりする行為が挙げられます。
このような強迫行為がエスカレートすると、「やめるともっと不安が強くなるのでは」という恐怖からやめられなくなり、周囲との関係や仕事、学業などにも支障をきたします。
強迫性障害を抱える患者に見られる行動

強迫性障害を発症すると、以下のような特徴的な行動が見られることがあります。
ご自身の行動が当てはまると感じた場合は、早めに専門機関へ相談することをおすすめします。
強迫性障害によく見られる行動例
・手が汚れていると過剰に気にして、何度も手を洗ってしまう
・特定の数字に強いこだわりがあり、その数字に合わせて行動してしまう
・ドアノブなどが不潔に思えて、触ることができない
・物の位置や配置に過敏になり、少しのズレでも強い不安を感じる
・外出時に鍵をかけたか不安になり、繰り返し確認しに戻ってしまう など
強迫性障害の治療方法
強迫性障害の治療では、「薬物療法」と「心理療法的」の2つを組み合わせて行うことが一般的です。
この2つの治療法を併用することで、不安や強迫行動の緩和を目指します。
それぞれの治療法には以下のような特徴があります。
薬物治療
強迫性障害の患者は、不安感や抑うつ状態に悩まされることが多く、治療には主に「選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)」が使われます。
症状が重い場合には、補助的に抗精神病薬が処方されることもあり、症状の改善を図ります。
心理療法
心理療法としては、「曝露反応妨害法(ERP)」という認知行動療法が特に効果的とされています。
この治療法では、患者をあえて不安を引き起こす状況に直面させ、強迫行動を抑える練習を重ねることで、不安に対する耐性を徐々に高めていきます。
最初は強いストレスを感じることもありますが、繰り返すうちにその状況に慣れ、自ら不安をコントロールできる力が養われていきます。
結果として、日常生活への支障を減らすことが可能になります。
強迫性障害セルフチェック

強迫性障害は、早めに治療を始めることで回復の見込みが大きく高まります。
ご自身の行動や考え方に違和感を覚え、もしかしたら強迫性障害かもしれないと感じている方は、まずは下記のチェック項目を活用して現状を振り返ってみてください。
複数の項目が当てはまる場合には、ひとりで悩まずに早めに当院へご相談いただくことをおすすめします。
初期の段階で適切なサポートを受けることで、日常生活への支障を減らし、より良い生活を取り戻す一助となります。